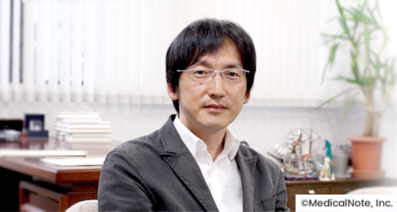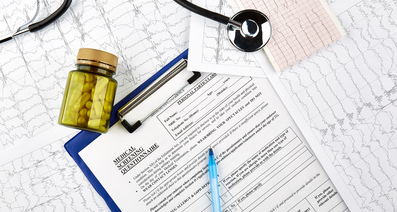
現代、「依存」という言葉はさまざまなシーンで使われます。しかし、「依存症」となると、これは精神医学における病気です。実際、この依存症とはどのような病気なのでしょうか? 社会生活と依存症の関係について、日本の精神医学におけるオピニオンリーダーである京都大学精神医学教室教授の村井俊哉先生にお話をお聞きしました。
社会生活と依存症
前回の記事「依存症とは(2)―依存症の歴史、どこまでが依存症か?」において、精神医学の診断基準であるDSM-5では、「行為・過程への依存症」として正式に依存症とされているのはギャンブル依存症のみであると説明しました。ギャンブル依存症のみである理由のひとつには、それ以外の行為・過程への依存症は、ほどほどであれば本人の健康問題としても社会問題としても、それほど深刻ではないという考え方があります。
前述のとおり、行為・過程に対する依存症には、ギャンブル依存症のほかにもいろいろな依存症があります。それらを精神疾患とするかどうかについては常に議論があります。趣味や嗜好がすべて精神疾患になったら、人生そのものが精神疾患になってしまうからです。そこで、精神医学の専門家の中ではこれらに対して線引きをしているわけです。
もちろん、精神疾患として定義されていないからといって問題がないと言いたいわけではありません。たとえば「いい歳をしたサラリーマンが電車の中で脇目もふらずゲームに没頭している。この国はいったいどうなってしまうのだろう?」という心配ももっともなことです。ただし、“病気に該当する”ということは、少なくとも日本においては健康保険で医療を受けることができるということです。「依存症が大きな問題である」ことと、「それに対して健康保険で医療を受けることができるかどうか」は別問題です。そうした理由もあって、しっかりとした線引きが必要なのです。
線引きの基本的な考え方のひとつは、どの程度その人の社会生活に悪影響をもたらすかという点にあります。「インターネットはどれだけ閲覧しても、寝不足で次の日に遅刻する程度の被害で済むが、ギャンブル依存症では短期間で全財産を失う可能性もある。だから前者は病気ではないが、後者は病気である」という考え方が合理性を持つのです。とはいえ、インターネット依存症であっても遅刻が重なり職場を回顧されるなど、社会生活に重大な影響が出る場合もあります。そのような理由もあって、現在病名として登録されていなくても、重症の人には何らかの治療や援助が必要だという意見も説得力を持っているのです。
アルコール依存症と、通常の飲酒者との間の線引きも簡単ではありません。実際、飲酒という行為自体は多くの人が行っています。それでも、その中で治療が必要なほど飲酒がやめられなくなる人は限られており、彼らのような状態に陥った人を「アルコール依存症(厳密な専門用語としては、『アルコール使用障害』)」と呼んでいるのです。違法薬物の場合は、それを使用した時点で少なくとも法律違反であり、もう少し境界がはっきりしますが、アルコールの場合はその境界があいまいなのです。
つまり、単に「お酒が好きな人」「競馬が好きな人」というレベルの人もたくさんいるわけです。本人がコントロールできる範囲であれば、それは人生において、趣味の一部として大切な時間になり得ます。ですから、「自分でコントロールできているのだから、病気扱いはしないでほしい」という意見は納得のいくものです。しかし、ここにもひとつ問題があります。それは、本人はコントロールできているつもりでも、客観的に判断するとコントロールできていない場合があることです。本人がどう感じているかだけではなく、周囲の人から見た視点も、単なる趣味・嗜好と依存症との違いを見極めるために大切なのです。
窃盗癖、放火癖は?
これらも、おそらくは行為・過程に対する依存症と呼んでよいでしょう。ただ、そもそもこういった行為はギャンブル依存症よりもはるかに問題が大きく、精神医学の歴史の中でも相当古い時代から、すでに病名として登録されています。
関連記事
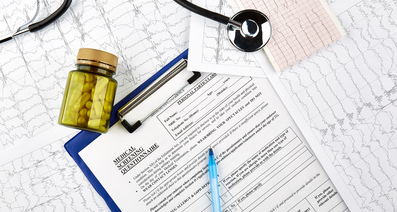

ギャンブル依存症(行為・過程に対する依存症)への診断と治療

依存症とは(4)―技術や文化とともに変化する依存症
関連の医療相談が13件あります
食欲不振とアルコール
ここ2週間ほど特に食事がとれません。せいぜい一日一食 。 たいしてこれに危機感も感じておらず、ぼーっとした状態をもて余しながらアルコール摂取しております。 現状として改善すべき状況なのか、教えてください。
下剤の服用について
下剤を規定以上服用しています。 下剤に依存し痩せ願望があるからです。 病院に受信するにも実習が重なりタイミングが見つからないので現在の症状をせめて改善したく相談しました。 下剤を5錠以上は2日に1度服用しています。 服用歴は4年か5年くらいだとおもいます。 今年に入ってから下剤乱用後 3日間の腹痛 下痢 吐き気 胸の圧迫感? 息苦しさが 3日から4日続きます。 下痢は下剤乱用すると必ずなってたのですが、今年は3日間ずっと下痢状態です。 どうゆう常体なのでしょうか、 なのにやめるべきことができなのです 病院への受診は7月になりそうでそれまで下剤を我慢できそうにありません。
買い物依存症?
ここ何年か、身体の不調や家庭、仕事が上手くいかなかったりのストレスから、ネットで買い物をしてカード払いにする為、借金が増えてしまいました。またその借金の返済に苦労してストレスが溜まり、発散のために同じ買い物行動を繰り返してしまいます。 やめようと思っても意志が弱いのかダメなんです。 自分は病気じゃないかと考えるようになりました。
昨日から始まった左目の円形型の黒い連続した点
ここ2週間位左まぶたの痙攣が続き、昨日より眼球に円形型の黒い点が幾重にも連なる様な残存が見えます。その他にも細かい点状の飛蚊症らしきものもあります。数年前から右目には軽度の飛蚊症の症状があるのですが、今回の左目は比較にならない程広範囲にまたがっていて、眼球全体が圧迫されるような違和感があります。緊急に眼科を受信した方が良いのか、アドバイスを頂きたいです。宜しくお願い致します。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「依存症」を登録すると、新着の情報をお知らせします